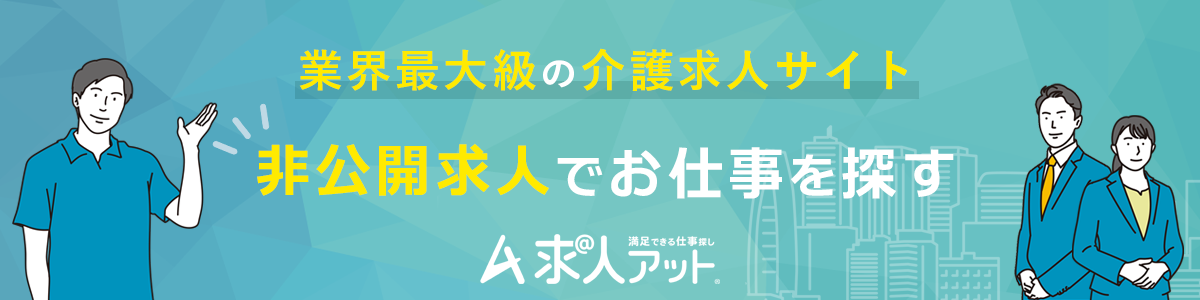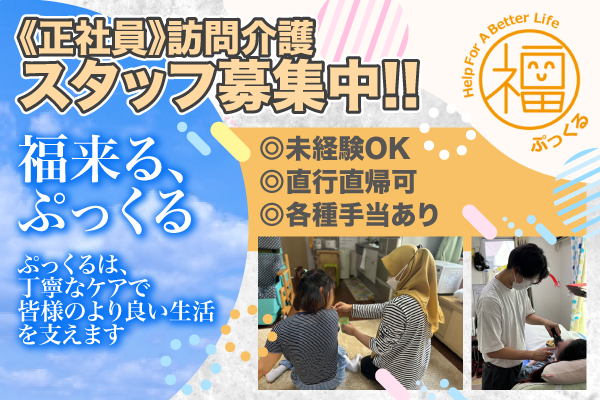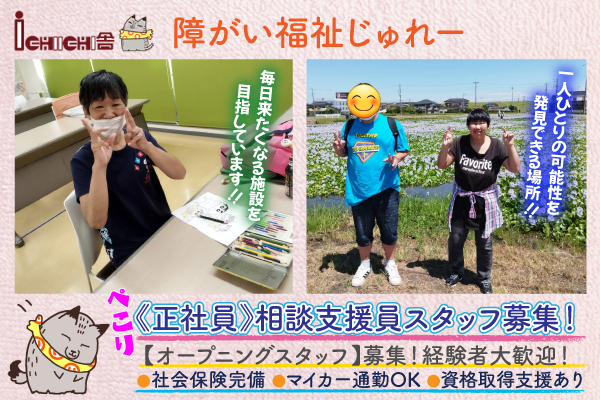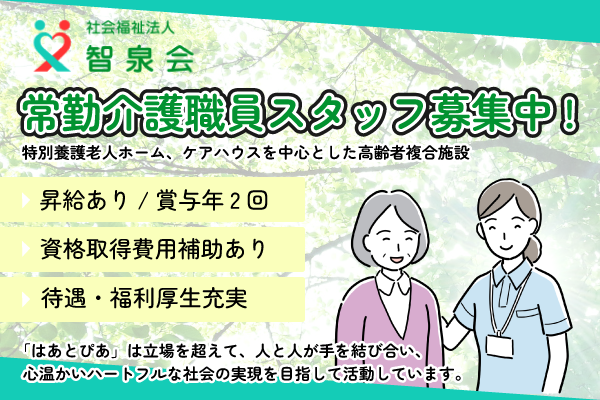介護施設や地域福祉の現場で、利用者や家族の悩みを聞き、最適な支援をつなぐ存在――それが生活相談員です。
介護職のように直接身体介助を行うわけではありませんが、施設の利用開始から退所後まで、すべての過程を支える重要な役割を担っています。
この記事では、福祉ジャンルにおける生活相談員の仕事内容、資格、年収、やりがい、そしてこれからの福祉現場で求められるスキルについて詳しく解説します。

生活相談員とは? ― 介護と社会をつなぐ“調整役”
生活相談員(せいかつそうだんいん)は、介護保険施設・デイサービス・特別養護老人ホームなどで、利用者・家族・行政・他職種との橋渡しを行う職種です。
介護現場では、介護職員や看護師が身体面を支え、生活相談員が“心と環境の調整”を行います。
つまり、福祉施設の「顔」であり、「窓口」であり、「司令塔」。
制度を理解し、人の気持ちに寄り添うスキルが求められる仕事です。
生活相談員の主な仕事内容
生活相談員の仕事は、一言で言うと「相談・調整・記録」。
日々、利用者や家族、職員、地域との間でさまざまなやり取りを行います。
- ① 相談対応:入所・通所希望者や家族の相談に対応し、制度やサービス内容を説明します。
- ② 契約・手続き:利用契約の締結、介護保険に関する書類作成、役所との連絡など。
- ③ 計画・調整:ケアマネジャー・看護師・介護士と連携し、個別支援計画(ケアプラン)をもとにサポート内容を調整します。
- ④ 家族との連絡:利用者の状況報告や面談、苦情・要望への対応。
- ⑤ 行政・地域との連携:市区町村、地域包括支援センター、医療機関などとの情報共有。
- ⑥ 行事・レクリエーション支援:利用者の生活を豊かにするためのイベント企画や運営も行います。
書類仕事や連絡業務も多く、介護現場の中では“デスクワークが中心の職種”とも言われますが、「人を支える仕事」である点に変わりはありません。
どんな施設で働くの?
生活相談員が活躍する職場は介護・福祉分野全体に広がっています。
- 特別養護老人ホーム(特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- デイサービス(通所介護)
- グループホーム
- ショートステイ
- 地域包括支援センター・福祉事務所
勤務先によって求められるスキルも少しずつ異なります。
例えば、デイサービスでは家族対応や送迎調整が多く、
特養では入退所手続きやケアカンファレンスの調整が中心になります。
生活相談員になるために必要な資格
生活相談員になるには、次のいずれかの資格・要件を満たす必要があります。
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
- 介護福祉士(自治体により可)
このうち最も一般的なのは「社会福祉主事任用資格」です。
大学や短大で福祉・心理・教育・社会学など指定科目を履修していれば、自動的に取得できるケースもあります。
また、民間施設では「介護福祉士+現場経験あり」でも生活相談員として採用されることがあります。
資格と経験、両方を活かせる職種といえるでしょう。
参考:日本社会福祉士会

生活相談員の1日スケジュール(デイサービスの場合)
- 8:30 出勤・送迎準備・利用者名簿の確認
- 9:00 利用者受け入れ・健康チェック
- 10:00 家族やケアマネジャーへの連絡・報告
- 12:00 昼食・記録作成・新規利用相談対応
- 14:00 利用者との面談・レクリエーション補助
- 16:00 送迎見送り・書類整理
- 17:30 翌日の準備・退勤
日中は利用者やスタッフとのやり取りが多く、夕方に記録業務や書類整理を行う流れが一般的です。
給与・年収
生活相談員の平均年収は350万〜450万円程度。
経験や勤務先によって差はありますが、安定した収入が見込める職種です。
- 新卒・未経験:月給20万〜23万円
- 経験者(5年以上):月給25万〜30万円
- 管理者・施設長クラス:月給35万〜45万円以上
また、社会福祉士や介護福祉士などの資格手当が付くケースも多く、
資格を活かしてキャリアアップがしやすいのも特徴です。
生活相談員のやりがい
- 利用者や家族から「ありがとう」と直接言ってもらえる
- 制度や知識を使って人の役に立てる
- 他職種との連携を通じてチーム医療・介護を支えられる
- 利用者の笑顔や回復に立ち会える
生活相談員は“感謝される機会が多い仕事”です。
ときには家族よりも深く利用者の想いに触れることもあり、
人の人生に寄り添う温かみを実感できる職業といえるでしょう。
生活相談員の大変なところ
- 相談内容が多岐にわたり、精神的な負担が大きい
- 利用者・家族・職員・行政との調整が難しい
- 書類作成・報告業務が多い
- クレーム対応などストレスがかかる場面もある
ただし、最近では相談員が一人で抱え込まないよう、
チーム支援・多職種連携が進んでおり、働きやすい環境づくりが広がっています。
向いている人の特徴
- 人の話を丁寧に聞ける
- 相手の立場で考えられる共感力がある
- コミュニケーションが好き
- 福祉制度・介護保険の知識を学ぶ意欲がある
- 調整力・折衝力がある
生活相談員は、「誰かのために行動できる人」にぴったりの仕事です。
人との関わりの中で成長したい人に向いています。

キャリアパスと将来性
生活相談員として経験を積むと、次のようなキャリアアップが可能です。
- 主任相談員:相談業務全体の統括・職員育成。
- 施設管理者・施設長:運営・人事・予算管理などマネジメントを担当。
- ケアマネジャー(介護支援専門員):相談員経験を活かして介護計画の作成に携わる。
- 地域包括支援センター職員:地域住民への総合的支援を行う行政系ポジション。
社会福祉士資格を取得すれば、より専門性の高い相談援助職(医療ソーシャルワーカーなど)への転身も可能です。
また、近年は福祉現場でデジタル記録やオンライン面談の導入が進み、ITスキルを持つ相談員が重宝されています。
これからの時代に求められる生活相談員像
超高齢社会の日本では、介護の形が「施設中心」から「地域・在宅支援」へと変化しています。
その中で生活相談員に求められるのは、単なる施設調整ではなく、地域全体を見渡す支援力です。
- 在宅介護や医療との連携
- 認知症サポートや予防活動への参加
- 地域ボランティアや家族会との協働
- ICTを活用した記録・情報共有
制度の知識だけでなく、「人と人をつなぐ力」「地域を支える力」が求められています。
まさに、“これからの福祉を形づくるキーパーソン”と言えるでしょう。
まとめ:生活相談員は“心のかけ橋”になる仕事
生活相談員は、介護や福祉の現場で利用者・家族・職員・行政をつなぐ大切な存在です。
制度を理解し、相手の想いに寄り添いながら、より良い暮らしをサポートする――
それは「人の人生に寄り添う福祉の原点」といっても過言ではありません。
相談員という名の通り、言葉を通して人を支える仕事。
相手の笑顔や「ありがとう」の一言が、何よりのやりがいになります。
生活相談員の求人をお探しなら、ぜひ求人アットで検索してみてください。
あなたの優しさと行動力が、誰かの“安心して暮らせる毎日”をつくる力になります。