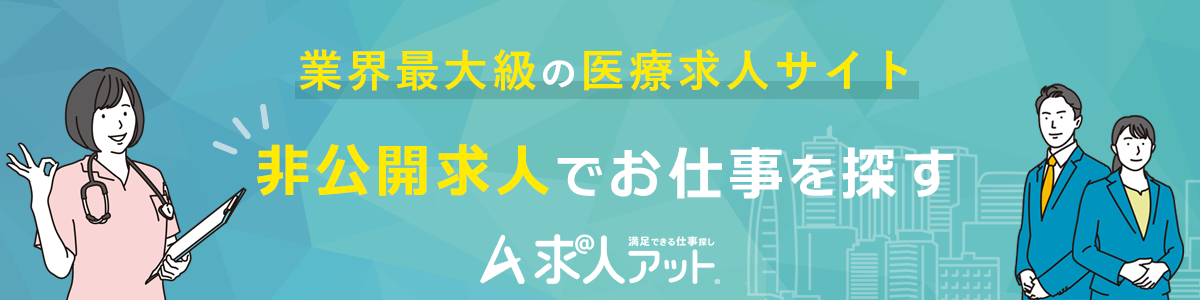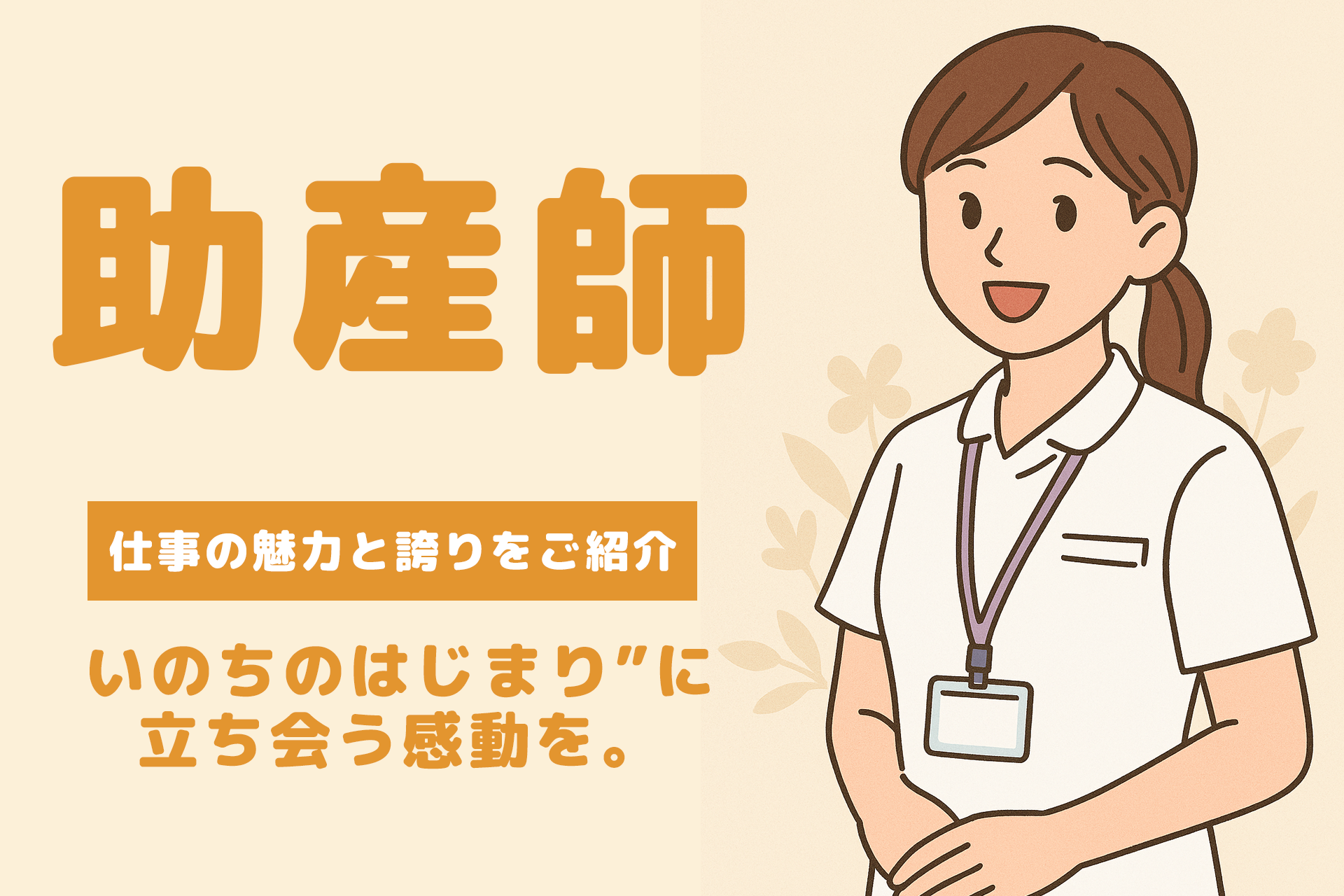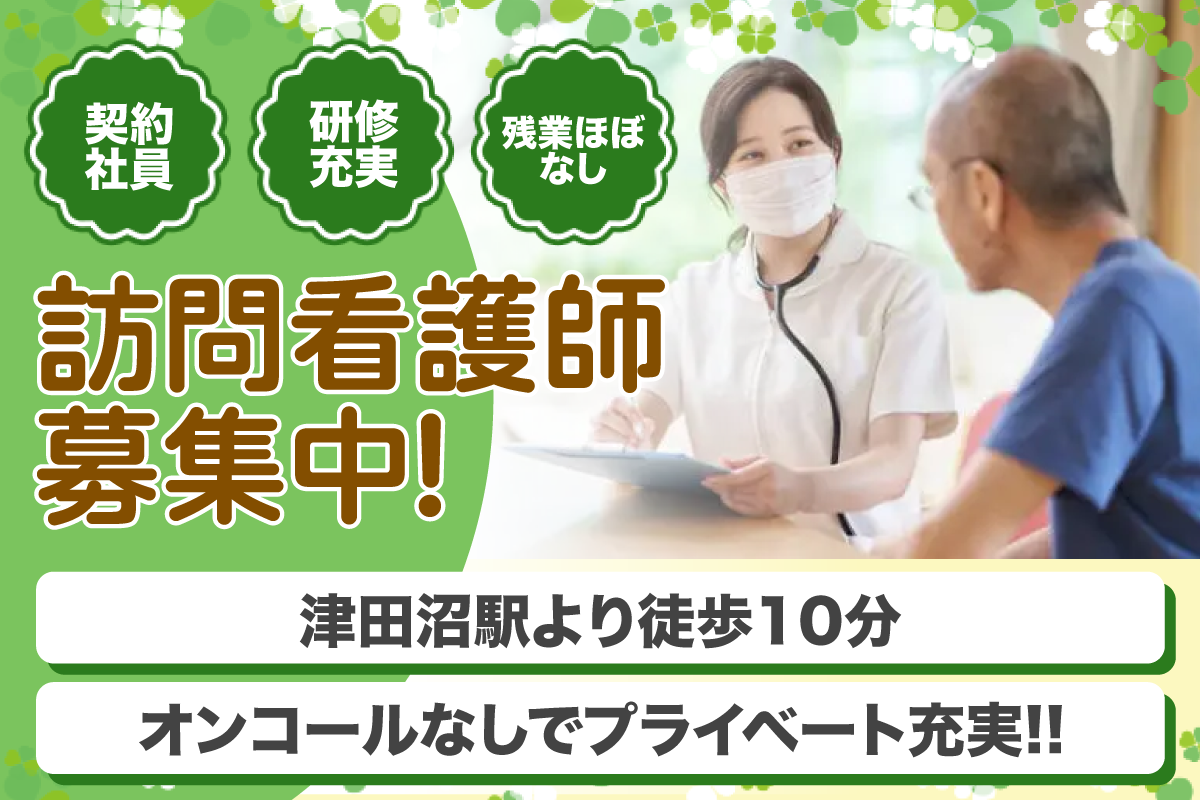言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist/ST)は、
「話す」「聞く」「食べる」といった、人が生活するうえで欠かせない機能を支える医療の専門職です。
脳卒中や外傷による失語症、神経疾患による嚥下障害、発声・構音障害などに対して、
医師や看護師、リハビリ専門職と協力しながら機能回復をサポートします。

医療の現場で働く言語聴覚士は、単に「話す練習」をする職種ではありません。
人が自分らしく生きるための“コミュニケーションの再構築”を支援する仕事です。
声を取り戻し、会話を取り戻し、食事を楽しめるようにする――
それが、医療分野におけるSTの使命です。
言語聴覚士(ST)とは?
言語聴覚士は、厚生労働省が認可する国家資格で、
言語・聴覚・発声・嚥下などに障がいを持つ方に専門的なリハビリを行う職種です。
医療現場では医師の指示のもと、検査や評価、リハビリ計画の立案・実施を行います。
対象となるのは、大きく以下の3分野に分けられます。
- 成人領域:脳血管障害(脳梗塞・脳出血)後の失語症、構音障害、嚥下障害など。
- 小児領域:発達遅延、聴覚障害、自閉スペクトラム症などによる言語発達支援。
- 高齢者領域:加齢や神経変性疾患(パーキンソン病、ALSなど)による発声・嚥下機能の低下へのリハビリ。
このうち、医療専門求人サイトで紹介されるST求人の多くは、
成人・高齢者領域に該当します。
医療機関やリハビリ病院、急性期・回復期・慢性期のいずれの段階でも重要な役割を果たしています。
医療現場でのSTの主な勤務先
- 総合病院・大学病院:急性期患者の嚥下評価・リハビリ、失語症リハビリ、検査業務。
- 回復期リハビリテーション病院:発症後のリハビリを中心に、在宅復帰を目指す支援。
- 療養型病院・クリニック:長期入院患者の維持的リハビリ、摂食嚥下訓練。
- 耳鼻咽喉科・言語外来:発声・聴覚障害への専門的介入。
- リハビリセンター・訪問リハビリ:退院後のフォローアップや地域支援。
近年は医療と地域の垣根が低くなり、
病院勤務のSTが在宅医療チームや介護施設と連携して支援するケースも増えています。
医療におけるSTの仕事の流れ
- 評価(アセスメント):発声・発語・理解・嚥下などの検査を行い、障害の程度を評価。
- 目標設定:患者の生活や希望を踏まえて、リハビリ計画を立案。
- 訓練・療法:発声練習、言語理解トレーニング、嚥下訓練などを個別に実施。
- チームカンファレンス:医師・看護師・リハビリ職と情報共有し、経過を分析。
- 退院支援・家族指導:自宅での食事や会話の方法を指導し、在宅移行を支援。
STの仕事は、検査→リハビリ→支援のサイクルを継続しながら、
患者の生活の中に「声」や「食べる喜び」を取り戻すことを目的としています。

医療分野でのSTの役割
医療分野でのSTの役割は大きく3つに分かれます。
- ① 言語機能の回復支援
脳梗塞や外傷性脳損傷などによる失語症・構音障害に対し、
発声・発語の訓練を通じて「伝える力」を再び育てます。 - ② 嚥下機能(のみこみ)の改善
食事中にむせる・飲み込みにくいといった症状に対し、
嚥下訓練や食形態の調整を行い、誤嚥性肺炎の予防にもつなげます。 - ③ コミュニケーション環境の整備
発話が難しい方に対して、ジェスチャーやタブレットなどの代替手段を提案し、
家族・医療スタッフとの意思疎通を支援します。
どの支援も「その人が自分らしく生きること」を目的としており、
医療の現場で最も人間的な職種の一つといわれています。
必要な資格とスキル
STになるには、文部科学省・厚生労働省指定の養成校(3〜4年制)を修了し、
国家試験に合格する必要があります。
医療分野では、さらに以下のようなスキルが求められます。
- 神経解剖学・音声言語学・嚥下生理の知識
- 医療チームでの連携力と情報共有スキル
- 患者・家族への説明力と共感力
- 評価・記録・データ分析の正確さ
特に嚥下評価に関しては、内視鏡検査(VE)やX線透視(VF)を扱う機会もあり、
医療安全の理解や臨床判断力も重要です。
医療現場でのSTの一日
- 8:30 出勤・申し送り・カンファレンス
- 9:00 嚥下評価検査・個別リハビリ
- 11:00 食事場面での嚥下観察・指導
- 13:00 午後の言語訓練・発話練習
- 15:00 退院前の家族指導・在宅サポート説明
- 16:30 記録・カンファレンス・翌日準備
病院のSTは、1日あたり6〜10名の患者を担当することが多く、
他職種との連携・調整業務も日常的に発生します。
給与・待遇・キャリア
医療分野のSTの平均年収は380〜500万円程度。
経験を積むと主任・リハビリ責任者・教育担当などに昇進でき、
年収600万円以上を目指すことも可能です。
勤務形態は日勤中心で、土日休やシフト制など働き方は施設によってさまざま。
また、医療分野で培った経験は、
在宅医療や地域リハビリなどの分野にも活かせます。
キャリアの広がりがある点も、STの魅力です。

チーム医療の中でのSTの存在
医療現場では、「言語聴覚士=コミュニケーションの専門家」としての役割が不可欠です。
医師・看護師・理学療法士・作業療法士などが連携する中で、
患者の“声”を最も近くで感じ取り、それを医療に伝える存在でもあります。
例えば、発語が難しい患者でも、わずかな表情やうなずきを読み取り、
医療チームに状態を共有する。
その観察力と共感力が、患者の回復を大きく支えています。
やりがいと魅力
STの仕事のやりがいは、言葉や食事という「人間の根幹」を支えられることです。
「また家族と話せるようになった」「好きなご飯が食べられた」――
その喜びを間近で感じられるのは、STだけの特権です。
また、患者だけでなく家族の不安を和らげ、
回復を共に喜べる“伴走者”としての存在でもあります。
医療の中で最も人の心に寄り添う職種の一つと言えるでしょう。
これからの医療と言語聴覚士
高齢化が進み、脳血管疾患・認知症・嚥下障害などが増加する中で、
言語聴覚士の需要は年々拡大しています。
厚生労働省の統計によると、STの就業者数は過去10年で約1.8倍に増加。
今後も病院・クリニック・在宅医療すべての領域で欠かせない存在になるでしょう。
さらに、AI・機器を活用した新しいリハビリ技術の導入も進んでおり、
デジタル時代のSTは「人+テクノロジー」の力で支援する時代へと変化しています。
まとめ:医療の現場で“声”と“生きる力”を取り戻す仕事
言語聴覚士(ST)は、単にリハビリを行うだけでなく、
人の尊厳と自立を取り戻す医療専門職です。
発語・嚥下・聴覚・コミュニケーション――どれも、人として生きるための大切な機能。
その回復を支える仕事には、確かな専門知識と温かい心が必要です。
「ありがとう」「おいしい」「また会おう」
――その一言が再び聞けるようになるまで、寄り添い続ける。
それが、医療の現場で働く言語聴覚士の誇りです。
言語聴覚士(ST) 求人をお探しの方は、
ぜひ求人アットで検索してみてください。
あなたの支える声が、誰かの人生を取り戻す力になります。
関連記事がありません。