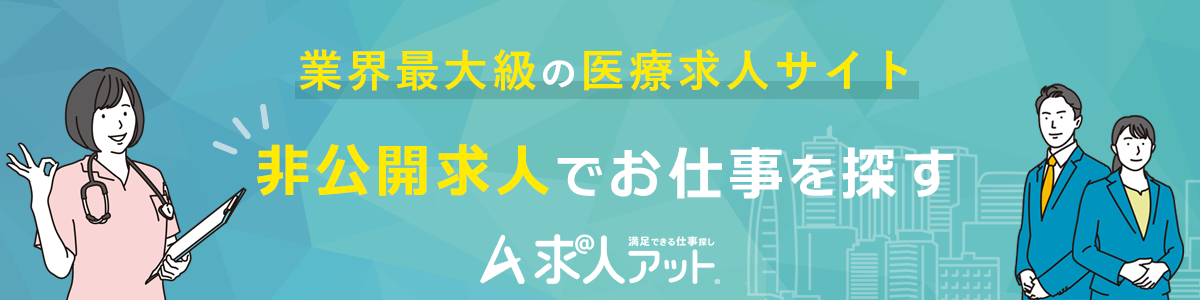人は誰かと話し、食事をし、想いを伝えることで生きています。
その“当たり前”を取り戻すために働くのが、言語聴覚士(ST:Speech Therapist)です。
言語聴覚士は、「話す・聴く・食べる・考える」といった、
人間の基本的な“コミュニケーション”と“摂食機能”を支えるリハビリ専門職。
病院・リハビリ施設・小児療育・在宅医療など、医療のあらゆる現場で活躍しています。
この記事では、医療分野における言語聴覚士の役割や仕事内容、
医療リハ職としてのやりがい、そして今後の展望について詳しく解説します。

言語聴覚士(ST)とは?
言語聴覚士は、国家資格を持つリハビリ専門職のひとつです。
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)と並んで「リハビリ3職」と呼ばれます。
対象となるのは、脳卒中や神経疾患などによる後遺症で
「話す・飲み込む・聞く・考える」ことが難しくなった人。
また、発達障害や難聴などで言葉の発達に遅れがある子どもも支援対象です。
つまりSTは、人と人との“つながり”を取り戻す仕事です。
医療現場での主な仕事内容
医療機関やリハビリ施設で働く言語聴覚士の仕事は多岐にわたります。
- ① 言語訓練:脳卒中・脳外傷・神経疾患などで言葉が出にくくなった患者への発話訓練。
- ② 構音訓練:発音や滑舌の改善を目指すトレーニング。
- ③ 失語症リハビリ:理解・表現・読字・書字能力の回復支援。
- ④ 摂食嚥下(えんげ)訓練:「食べる」「飲み込む」機能のリハビリ。食形態の調整や姿勢指導も行う。
- ⑤ 高次脳機能障害の支援:注意・記憶・判断などの認知機能回復をサポート。
- ⑥ 聴覚リハビリ:人工内耳・補聴器利用者への聴覚トレーニング。
STは患者一人ひとりの症状や生活背景を丁寧に把握し、
医師・看護師・PT・OT・管理栄養士などとチームを組んでリハビリを進めます。
医療分野で働くSTのフィールド
言語聴覚士は、医療業界の中でも特に幅広い現場で必要とされています。
- 病院(急性期・回復期・慢性期):発症直後のリハビリや退院前の機能回復を支援。
- リハビリテーションセンター:脳卒中・神経難病など長期的な機能回復をサポート。
- 小児発達支援センター:発達障害や言葉の遅れがある子どもの言語訓練。
- 耳鼻科・聴覚センター:難聴・補聴器・人工内耳の適応指導。
- 訪問リハビリ:在宅療養者への摂食・言語支援。食事姿勢の調整や介護職への指導も。
このように、医療STは乳児から高齢者まで、すべてのライフステージに関わる職業です。
言語聴覚士に求められるスキル
STの仕事は「人と向き合う力」がすべての基礎です。
同じ症状でも、患者の年齢・性格・生活環境によってリハビリの進め方は異なります。
- 観察力:わずかな表情や声のトーンから変化を読み取る。
- 傾聴力:患者や家族の不安・希望を受け止める。
- 説明力:専門的な訓練内容をわかりやすく伝える。
- 協調性:チーム医療の一員として他職種と連携する。
また、嚥下(えんげ)領域では、
看護師や管理栄養士と協力して「安全に食べる」ための環境づくりを担います。
単にリハビリを行うだけでなく、
患者の“生活全体”を考えた支援が求められる職種です。
医療現場でのSTの1日(回復期リハビリ病棟の例)
- 08:30 出勤・朝のミーティング・担当患者の状態確認
- 09:00 嚥下訓練(飲み込み・姿勢調整など)
- 10:30 言語リハビリ(発声・構音・会話訓練)
- 12:00 昼食介助・食事観察(安全な摂食確認)
- 13:30 リハビリカンファレンス・他職種連携
- 15:00 失語症患者の個別訓練・家族指導
- 17:00 記録・翌日の準備・退勤
1日に10〜15人ほどの患者を担当するケースが多く、
一人ひとりとじっくり関われるのが特徴です。

医療分野におけるSTの重要性
近年、脳血管疾患や神経変性疾患(ALS・パーキンソン病など)の増加に伴い、
STの需要は全国的に高まっています。
また、2024年の介護保険・診療報酬改定では、
嚥下評価・言語訓練の記録が「科学的介護情報システム(LIFE)」に統合され、
データに基づくリハビリが求められるようになりました。
つまりSTは、医療と介護をつなぐ“架け橋”的な存在でもあるのです。
小児・高齢者・在宅での活躍領域
小児分野
発達障害・構音障害・聴覚障害のある子どもへの支援。
言葉の発達を促すだけでなく、親子の関係づくりもサポートします。
高齢者分野
脳梗塞後の失語症や嚥下障害など、加齢や疾患に伴う機能低下を改善。
「食べる喜び」「会話する喜び」を取り戻すリハビリを行います。
在宅・地域分野
訪問リハビリや地域包括支援センターでの活動も増加中。
在宅療養者の口腔ケアや介護職への指導、地域の健康講座などに関わることもあります。
STは病院内だけでなく、地域全体をフィールドに活躍しています。
キャリアアップと将来性
言語聴覚士の国家資格取得者は全国で約4万人。
まだ数が少ないため、需要は高く、就職・転職市場でも安定した人気を保っています。
- 専門分野(摂食嚥下・小児・高次脳機能など)のスペシャリストへ
- 教育・研究・講師として後進育成に関わる
- 訪問リハや在宅支援分野で独立開業も可能
また、医療と福祉の連携が進む今、
STが介護施設や在宅分野に関わる機会もさらに広がっています。
この仕事に向いている人
- 人の話を丁寧に聞ける人
- 根気強くサポートを続けられる人
- 細かい変化に気づける観察力がある人
- 「ことば」「食べる」ことに興味がある人
技術よりもまず、「相手の人生を支えたい」という思いが何よりも大切です。

まとめ:言葉と食事を支える、医療の温かいプロフェッショナル
言語聴覚士(ST)は、医療の中で“命を支える”というよりも、
“生きる喜びを取り戻す”仕事です。
失われた言葉が少しずつ戻り、家族と再び会話できた瞬間。
長い訓練の末に、初めて「ごはんを食べられた」瞬間。
その笑顔こそ、STにとって最高の報酬です。
医療の現場で、患者と家族の“声”をつなぐ仕事。
それが言語聴覚士という職業です。
言語聴覚士(ST)の求人をお探しなら、ぜひ求人アットで検索してみてください。
あなたの支える声が、誰かの「生きる力」になります。
関連記事がありません。