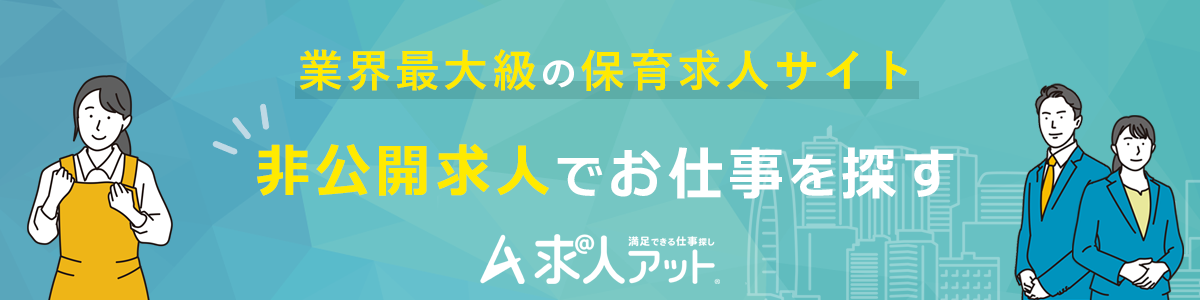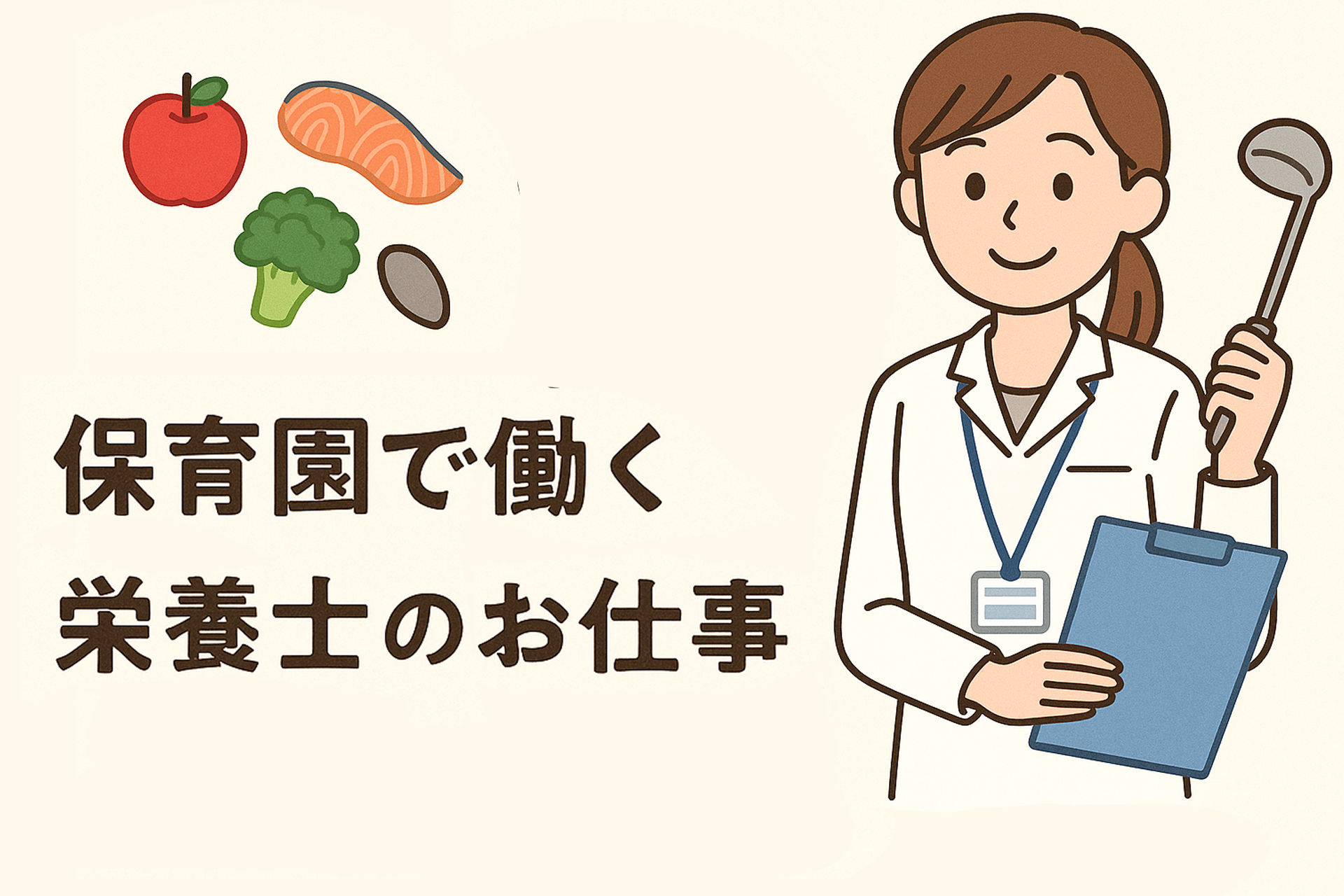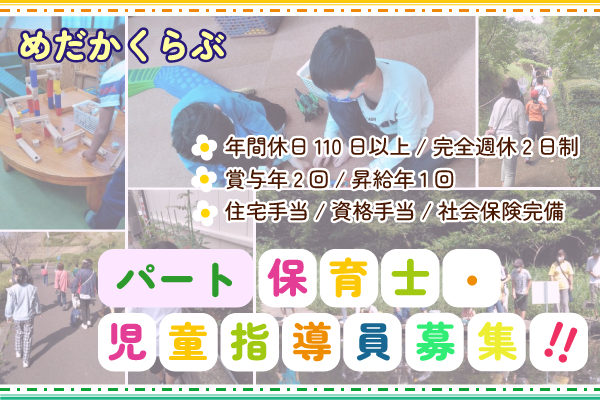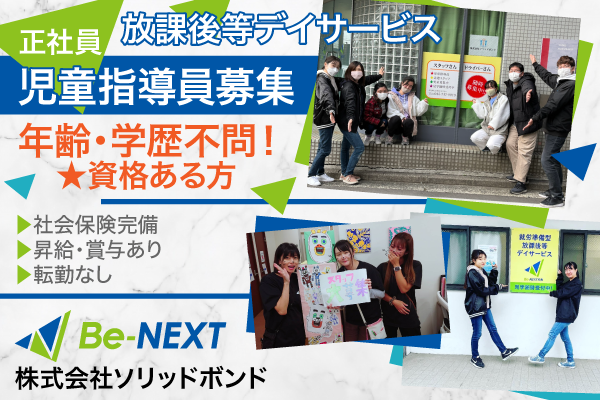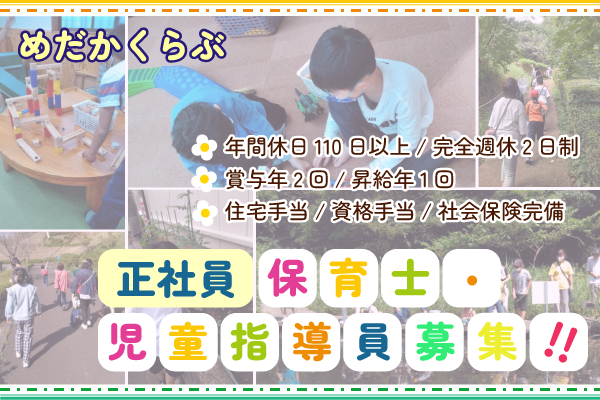「ことばを育てる専門家」と聞いて、どんな仕事を思い浮かべますか?
医療やリハビリの分野で活躍する言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist:ST)をイメージする方が多いかもしれません。しかし近年では、保育園や幼稚園といった子どもたちの成長の場でも、STの力が求められるケースが増えています。
発達の多様化が進み、言葉の遅れやコミュニケーションの難しさに寄り添える専門職の存在は、子ども本人だけでなく、保護者や保育者にとっても心強い支えとなります。
本記事では、言語聴覚士(ST)の役割や仕事内容、保育の現場における必要性、キャリアの可能性について解説し、最後に求人情報の探し方もご紹介します。

言語聴覚士(ST)とは?
国家資格としての位置づけ
言語聴覚士は、ことば・聴覚・発声・嚥下に関するリハビリテーションを行う国家資格を持つ専門職です。1997年に制定された比較的新しい資格で、医療・福祉・教育など幅広い分野での活躍が可能です。
STの役割
- 子どもの「ことばの発達支援」
- 発音の改善や吃音への対応
- 聴覚障害児への補聴器・人工内耳を活用した指導
- 摂食・嚥下機能のトレーニング
- 保護者や保育者への助言
単なるリハビリ職にとどまらず、子どもが社会で自分らしく生きるためのコミュニケーション力を育てる専門家といえます。
保育の現場でSTが必要とされる背景
発達障害の理解と支援の広がり
文部科学省や厚生労働省の調査によると、発達障害のある子どもの割合は6〜8%程度といわれています。実際にはグレーゾーンを含めるとさらに多く、園児のクラスに1〜2人は「ことばの発達が気になる子」がいるのが現状です。
保護者からのニーズの高まり
「うちの子、まだ2語文を話さないけど大丈夫?」「発音が聞き取りにくいのは自然に治るの?」
こうした保護者の不安に、科学的根拠に基づいて答えられる存在がSTです。
専門職配置の制度拡充
インクルーシブ教育や保育の理念が浸透するなかで、自治体によっては専門職配置の補助金が整備され、STが保育園やこども園に非常勤として関わるケースが増えています。
言語聴覚士の具体的な仕事内容(保育領域)
- 発音練習(サ行やカ行が言いにくいなど)
- 吃音の子どもへのリズムを使った発話練習
- 絵カードを使った語彙の拡大支援
- 嚥下の発達に課題がある子への食事指導
- ことば遊びや歌を取り入れた集団支援
- 保護者・保育者への家庭での支援方法の助言

言語聴覚士として働く魅力
STは子どもの成長を間近で感じられるだけでなく、保育士や心理士、看護師などとチームで子どもを支えるやりがいがあります。さらに、保育園勤務だけでなく、児童発達支援や医療機関、独立開業などキャリアの幅が広いのも特徴です。
年収と働き方
ST全体の平均年収は約400万円前後とされます。保育園勤務なら300万〜450万円、医療機関なら500万円近いケースも。
また、非常勤や複数施設での勤務など、柔軟な働き方が可能で、子育て中の方も働きやすい職種です。
今後の需要と将来性
発達障害児の早期支援やインクルーシブ教育の推進により、保育現場でのST需要はますます高まると予想されます。
STを目指すには
大学や専門学校で3〜4年学び、国家試験に合格することで資格が得られます。社会人から学び直すケースや、保育士からSTへのキャリアチェンジを目指す方も増えています。
STに向いている人
- 子どもや人との関わりが好き
- ことばや音声に興味がある
- コツコツ努力できる
- 相手の気持ちに寄り添える

まとめ ― 保育の現場でSTとして働く魅力
言語聴覚士(ST)は、子どもたちの「ことばの未来」を支える大切な存在です。保育の現場で関わることで、子どもが自分らしく表現できる環境を整え、成長の喜びを共に分かち合えるのが魅力です。
求人を探すなら「求人アット保育」で!
もしあなたが言語聴覚士(ST)として保育の現場で活躍したいと考えているなら、専門求人サイトを活用するのが近道です。
「求人アット保育」では、保育園・こども園・児童発達支援事業所など、STが活躍できる求人情報を多数掲載中です。