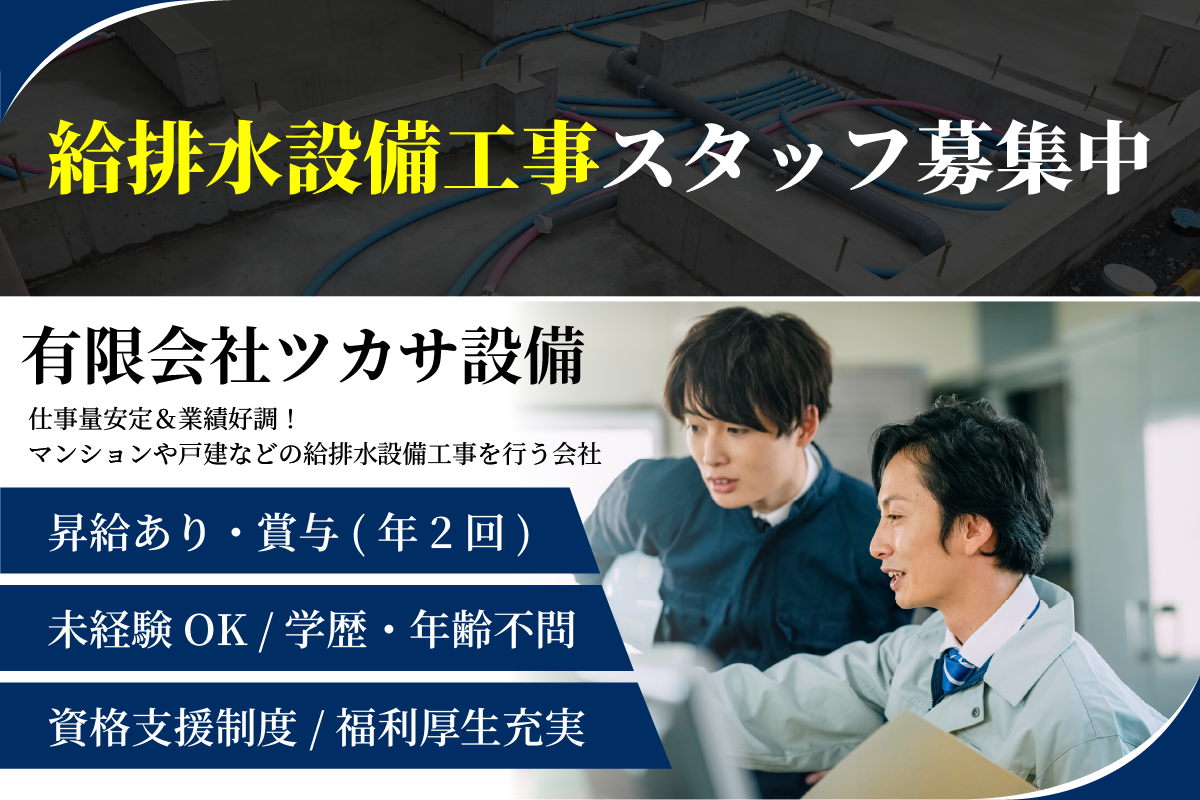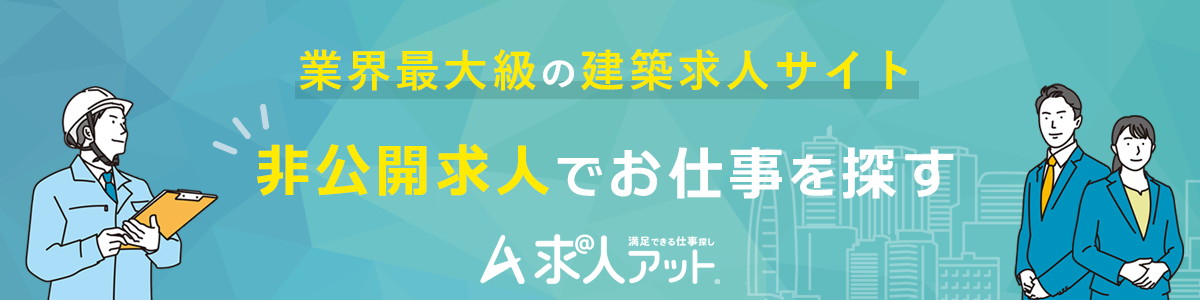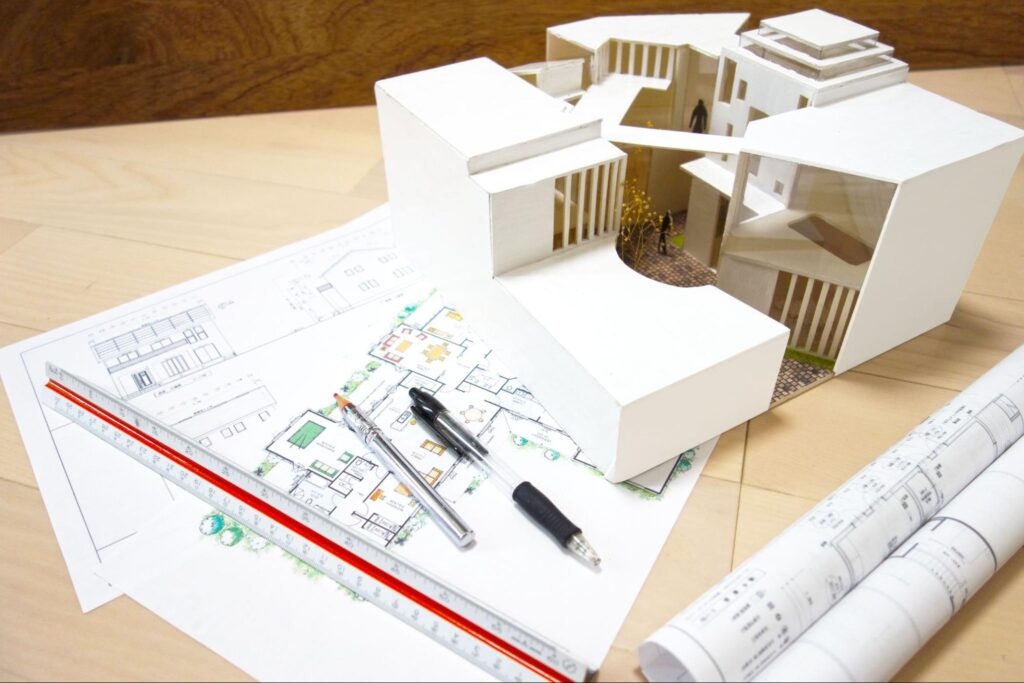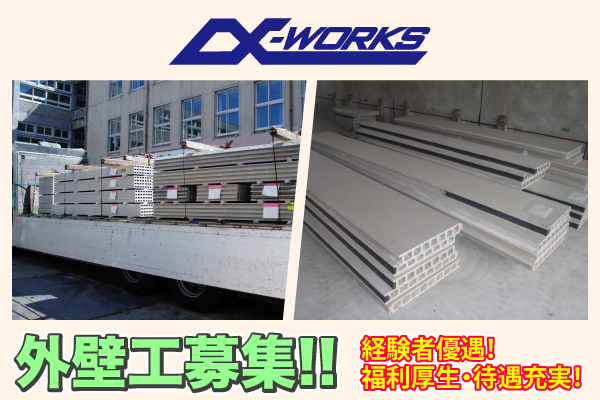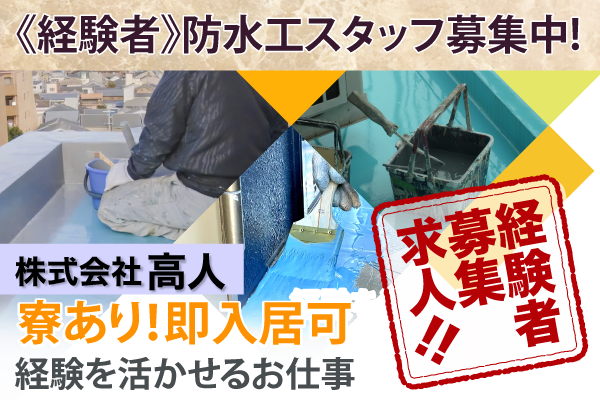エネルギー管理士は、エネルギーや電気の使用の管理や最適化を図るために欠かせない国家資格です。本記事では、エネルギー管理士資格の取得方法や具体的な仕事内容、勉強方法、転職やキャリアアップへの活かし方まで詳しく解説します。
- エネルギー管理士とは?
- エネルギー管理士ができた背景と理由
- エネルギー管理者とエネルギー管理員の違い
- 第一種エネルギー管理指定工場と第二種エネルギー管理指定工場の違い
- エネルギー管理士の仕事内容
- エネルギー管理士の資格を取る方法
- エネルギー管理士試験での取得
- エネルギー管理士研修での取得
- エネルギー管理士資格を取得するメリット
- エネルギー管理士はキャリアアップに有利な資格
- 資格手当や年収アップが期待できる
- エネルギー管理士の需要は今後ますます高まる
- 環境対応が進む中で注目される国家資格
- エネルギー管理士の取得におすすめの勉強方法
- エネルギー管理士試験の過去問対策を徹底
- 独学が不安な人は通信講座・オンライン講座で対策
- エネルギー管理士の参考書・書籍の活用法
- エネルギー管理士に関するQ&A
- エネルギー管理士に向いている人は?
- エネルギー管理士に関連する資格は?
- エネルギー管理士の資格を転職活動に活かすには?
- 「求人アット建築」でエネルギー管理士の求人を見つける!
- エネルギー管理士はエネルギーを管理する重要な仕事
エネルギー管理士とは?
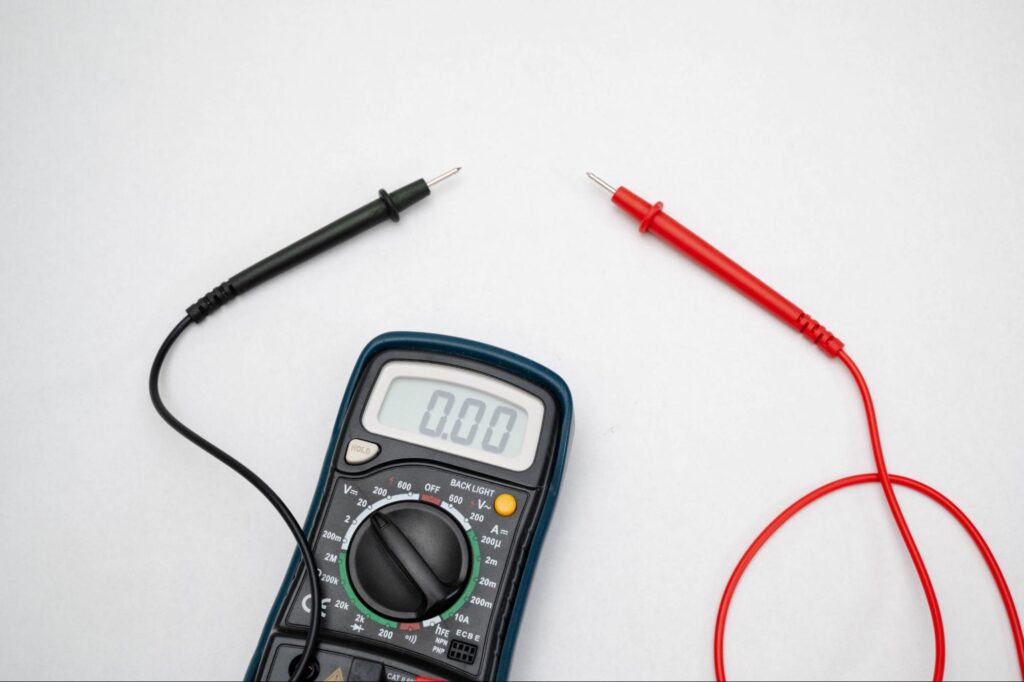
エネルギー管理士は、エネルギーや電気の使用を管理する国家資格です。エネルギーの使用状況を分析し、無駄を省いてコストを削減するための改善策を提案・実施する役割を担います。工場、オフィスビル、病院など、さまざまな施設で求められる重要な人材です。
エネルギー管理士ができた背景と理由
エネルギー管理士はもともとは、熱管理士・電気管理士に分かれていましたが、2006年に省エネ法が施行された際に「エネルギー管理士」の資格が生まれました。
1970年代のオイルショック以降、日本ではエネルギー資源の有効活用が国家的課題となりました。これを受けて、エネルギーの使用を最適に管理できる専門人材の育成と配置が求められるようになり、エネルギー管理士という国家資格制度が制定されました。
エネルギー管理者とエネルギー管理員の違い

エネルギー管理者と似た名称に「エネルギー管理員」がありますが、両者は制度上の役割が異なります。エネルギー管理士は、一定以上のエネルギーを使用する事業者に対して配置が義務付けられる国家資格保持者であり、より高度な知識と実務経験を求められます。一方、エネルギー管理員は、エネルギーの使用が少ない施設などに配置される職種で、必ずしも資格を必要としません。
| エネルギー管理者 | エネルギー管理士の資格取得が必要
「第一種エネルギー管理指定工場」は選任必要 |
| エネルギー管理員 | エネルギー管理士の資格取得が必須ではない
「第二種エネルギー管理指定工場」は選任必要 |
第一種エネルギー管理指定工場と第二種エネルギー管理指定工場の違い
| 第一種エネルギー管理指定工場 | エネルギー使用量(原油換算)が年間3,000kl以上 |
| 第二種エネルギー管理指定工場 | エネルギー使用量(原油換算)が年間1,500kl以上3,000kl未満 |
エネルギー管理士の仕事内容

エネルギー管理士の主な業務は、施設内で使用される電気やガス、燃料などのエネルギー消費状況を把握し、無駄をなくすための対策を講じることです。
エネルギー使用状況のモニタリング、省エネ設備の導入検討、エネルギー使用の効率化提案、関係法令への対応などを担います。また、昨今では環境への配慮が重視されており、温室効果ガス排出削減の観点からもエネルギー管理士の役割が強く求められています。
エネルギー管理士の資格を取る方法
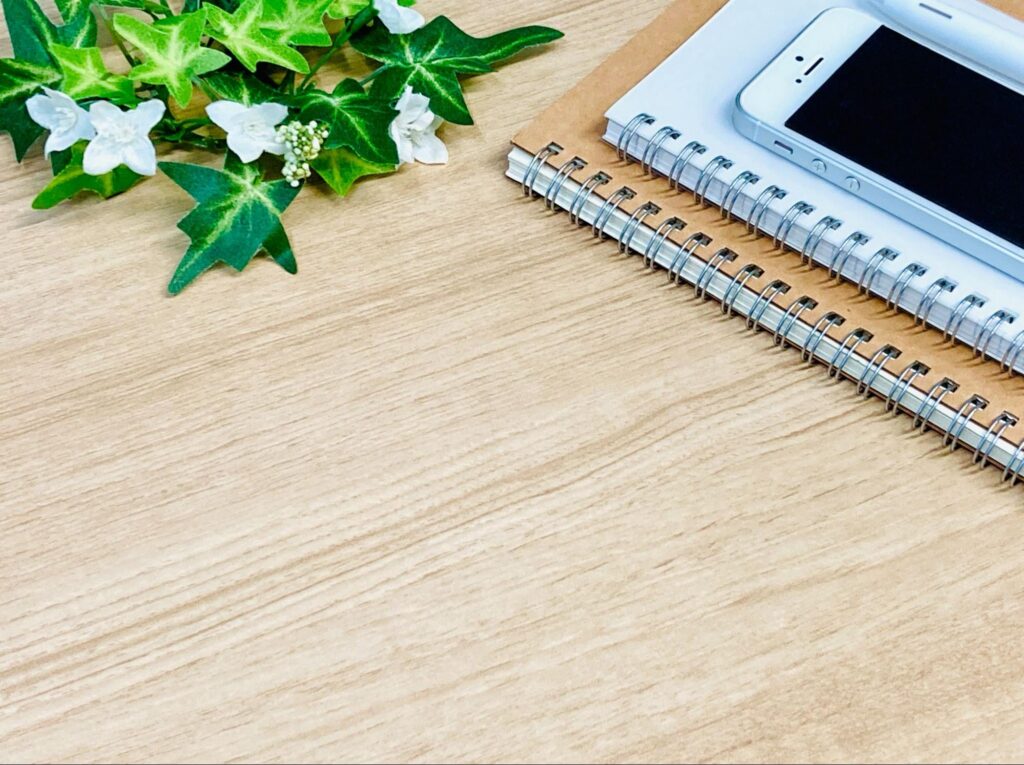
エネルギー管理士の資格取得には、主に以下の2つの方法があります。具体的に取得方法を紹介するので、参考にしてみてください。資格に関する情報は日々変化し続けていますので、実際に資格取得に取り組む前には、最新の情報を確認しましょう。
エネルギー管理士試験での取得
経済産業省の認定試験である「エネルギー管理士試験」に合格することで資格を取得できます。エネルギー管理士試験の受験に際して、資格の制限はありません。
| 受験資格 | なし |
| 試験形式 | マークシート |
| 試験内容 | 必須基礎区分+選択専門区分:(熱分野)or(電気分野) |
| 合格率 | 令和3年度:31.9%、令和4年度:33.9% |
| 受験手数料 | 17,000円(*条件を満たす場合は10,000円) |
第47回エネルギー管理士試験の内容はこちらになります。【必須共通科目】に加えて、熱分野か電気分野の得意な方を選択し、取り組む形です。
【必須共通科目】
| エネルギー総合管理及び法規 | 80分 |
【熱分野】
| 熱と流体の流れの基礎 | 110分 |
| 熱利用設備及びその管理 | 110分 |
| 燃料と燃焼 | 80分 |
【電気分野】
| 電気設備及び機器 | 110分 |
| 電力応用 | 110分 |
| 電気の基礎 | 80分 |
国家試験による取得フローは下記になります。公式ページを受験前に確認するようにしましょう。
- 一般財団法人省エネルギーセンター(経済産業大臣が指定した試験機関です。)が毎年8月に行うエネルギー管理士試験に合格する。試験はどなたでも受けられます。試験はマークシート方式です。
- 免状申請の際に、エネルギーの使用の合理化に関する実務に1年以上従事したことを証する「エネルギー使用合理化実務従事証明書」の提出が必要となります。実務に従事した時期は、合格の前後を問いません。
- 経済産業大臣に申請することにより、エネルギー管理士免状が交付されます。
- 受験申込みから免状取得までの流れ(フロー図)
- 課目合格制度について(試験)
エネルギー管理士研修での取得
一定の実務経験がある場合、試験ではなく研修を受講することで資格を取得することも可能です。これを「エネルギー管理研修制度」と呼び、所定の講義・実習を修了した後に認定されます。受講資格として、エネルギーの使用に関する業務に3年以上携わっていることなどが求められます。
認定研修による取得フローは下記になります。試験での取得同様に、公式ページを受験前に確認するようにしましょう。
- エネルギー管理研修を受けるためには、研修申込時までにエネルギーの使用の合理化に関する実務に3年以上従事していることが必要です。
- II 一般財団法人省エネルギーセンター(経済産業大臣が登録した研修機関です。)が毎年12月に行うエネルギー管理研修を受講し、修了すること。(修了試験に合格すること。)修了試験は記述式です。
- 経済産業大臣に申請することにより、エネルギー管理士免状が交付されます。
- 受験申込みから免状取得までの流れ(フロー図)
- 課目合格制度について(試験)
エネルギー管理士資格を取得するメリット
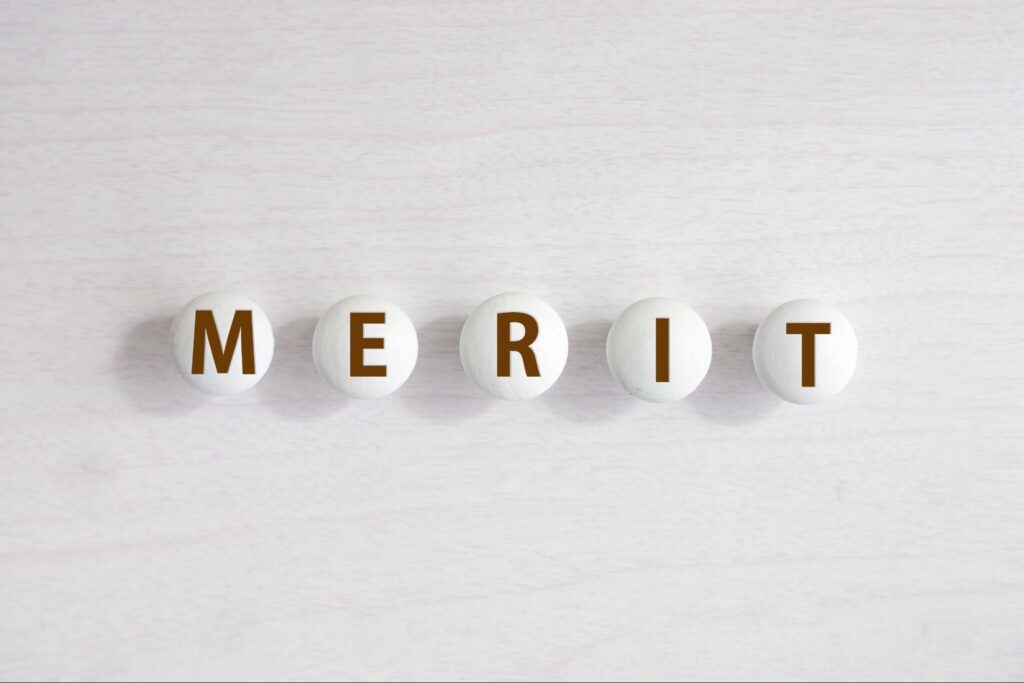
エネルギー管理士の資格を取得することで、省エネに関する専門知識と実務能力が証明され、企業内外での評価が高まります。国家資格であるため信頼性も高く、転職・キャリアアップにも有利に働きます。ここでは、エネルギー管理士資格を取得するメリットを紹介します。
エネルギー管理士はキャリアアップに有利な資格
エネルギー管理士の資格を保有することで、企業の省エネ推進部門や設備管理部門での昇進や異動がしやすくなります。特に、製造業やビル管理業などでは、法定で有資格者の配置が求められるため、資格者のポジションは安定しています。
資格手当や年収アップが期待できる
エネルギー管理士の資格があると役立つ職場では、エネルギー管理士の資格を取得すると月額で数千円〜1万円程度の資格手当が支給されるケースがあります。また、エネルギーコスト削減や環境対策に貢献できる人材として、年収のベースアップや評価向上につながることもあります。
エネルギー管理士の需要は今後ますます高まる
近年は、地球温暖化対策やカーボンニュートラルの流れを受けて、企業のエネルギー管理体制が厳格化しています。その中で、エネルギーの使用状況を把握・改善できる「エネルギー管理士」の需要は、今後も継続的に伸びていくと予想され、採用ニーズも高まると予想されます。
環境対応が進む中で注目される国家資格
エネルギー管理士は、省エネルギー法に基づいて認定される国家資格であり、信頼性の高い技術者として業界内で重宝されます。SDGsやESG経営など環境意識の高まりに伴い、エネルギー管理士の社会的意義も増しています。
エネルギー管理士の取得におすすめの勉強方法
エネルギー管理士試験に合格するためには、効率的な学習計画が欠かせません。自分のペースに合った学習スタイルを見つけることが、合格への近道です。ここでは、おすすめの勉強方法を紹介します。
エネルギー管理士試験の過去問対策を徹底
過去問題の分析は非常に効果的で、エネルギー管理士試験の出題傾向を掴むことができます。繰り返し解くことで頻出テーマや問われ方のパターンを把握でき、対策が立てやすくなります。
独学が不安な人は通信講座・オンライン講座で対策
独学での勉強が難しいと感じる場合は、通信講座やオンライン講座の利用を検討しましょう。プロの解説付きで学べるため、理解が深まりやすく、効率的な学習が可能です。最近ではスマホで学べる講座もあり、スキマ時間を有効活用できます。
エネルギー管理士の参考書・書籍の活用法
基礎を固めるには、信頼できる参考書やテキストの活用が不可欠です。レビューや評価を確認して、自分に合った一冊を選びましょう。図解付きの書籍や初心者向けのものを選ぶと、より理解しやすくなります。
エネルギー管理士に関するQ&A

エネルギー管理士に向いている人は?
エネルギー管理士に向いているのは、理系分野に関心があり、論理的思考が得意な人です。また、省エネや環境問題に関心があり、現場での観察力や改善提案を行うコミュニケーション力がある人も適しています。
エネルギー管理士に関連する資格は?
エネルギー管理士と関連性の高い資格としては、「電気主任技術者」「冷凍機械責任者」「建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)」などがあります。これらを併せて取得することで、より広範な設備管理・省エネ関連の業務に対応できるようになります。
エネルギー管理士の資格を転職活動に活かすには?
エネルギー管理士資格は、転職市場でも評価が高く、工場・病院・大型施設などでの求人が多数存在します。資格取得後は、求人サイトや転職エージェントを活用して、省エネ対応が求められる業種を中心に情報収集を行うと良いでしょう。
「求人アット建築」でエネルギー管理士の求人を見つける!

エネルギー管理士の仕事を探すなら、求人サイトの中でも「求人アット建築」がおすすめです。高年収案件や資格を活かせる求人が多数掲載されており、自分に合った仕事を探しやすいです。
「求人アット建築」
エネルギー管理士で働くことを考えている方は、「求人アット建築」などの専門の求人・転職サイトを利用するのがおすすめです。通常の求人サイトより、専門の求人・転職サイトは、より専門的な内容を記載しているケースが多く、求人を探しやすいです。
エネルギー管理士はエネルギーを管理する重要な仕事

エネルギー管理士は、省エネルギーが求められる現代社会において非常に重要な国家資格です。資格を取得することで、エネルギーの専門家としてのキャリアアップや転職が可能になります。本記事で紹介した取得方法や勉強法、活用方法を参考に、ぜひエネルギー管理士への第一歩を踏み出してみてください。